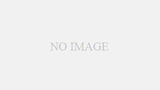~お金持ちになれる黄金の羽の拾い方2015~知的人生設計のすすめ~
基本情報
- 著者:橘玲
- 読了日:2025/9/16~9/25
- きっかけ: 転職や副業を考える人生の岐路に立っており、これから進む道での後悔を減らすためにまずはお金の基礎知識をつけようと考えたため
読む目的
①お金を稼ぐ、増やす手段の収集
②お金、経済の基礎知識を身に着ける
はじめに
「お金持ちになる」ことは、単なる夢物語ではありません。それは、知識と戦略によって達成できる現実的な目標です。橘玲氏の『黄金の羽』は、そのための地図を与えてくれる、まさに羅針盤のような一冊です。この記事では、PrologueからEpilogueまで、本書の独自の構成に沿って、各章の重要なポイントと、あなたの人生に役立つ具体的なヒントをまとめました。
この記事を読めばわかること
- お金持ちになるための「思考法」とは何か。
- なぜ、給料だけでは資産が増えないのか。
- 「マイクロ法人」が、現代の個人にとって最強の武器となる理由。
- 人生の幸福度を高める「働き方」のヒント。
Part 0:黄金の羽ができるまで
- 要約:
- 知識社会では情報は共有され、その情報を的確に入手し活用すれば近道ができる。ゲームを楽しむにはゲームのルールをよく知る必要があるということだ。それができない人は回り道をするか、金を払う必要がある。黄金の羽とは構造的な歪みから生まれる差異によって利益を得る方法であり。著者は出版業界の流通構造の歪みから黄金の羽をみつけた。国家の市場介入は歪みを生む典型例であり、日本でも大麻や、高金利貸し、風俗産業などが該当する。本書ではサラリーマンに利用できる「個人」と「法人」の国家制度歪みから黄金の羽を見つける方法を指南する。
- 気づき・学び:
- 社会の構造などには全く興味を抱かない人生だったが、この章を読んだだけで、社会の構造を理解したくなった。
- ポイントはよく知るということで、表面的に知っているだけでは意味のないことを理解した。
Part 1:人生を最適設計する「資産運用」の知識
1節 世界に一つしかないお金持ちの方程式
- 要約:
- お金持ちの方程式は”資産形成=(収入ー支出)+(資産×運用利回り)”である。初期では純利益(収入ー支出)の確保、特に支出を減らすことが大事。住居コスト、生命保険費から見直すべき。サラリーマンは払う税金が多いため、自営業や副業で稼ぐのが支出を減らす良い方法。投資する際は手数料が極めて少ない方法(ネット経由)で実施するべき。
- 詳細要約:
- お金持ちの方程式は資産形成=(収入ー支出)+(資産×運用利回り)
- 他人への投資(インカム、キャピタルゲイン)と自分への投資(自分の能力)を天秤にかける。初期は後者への投資が経済合理的
- 確実にお金持ちになる方法は支出を減らすこと、特に住宅コストと生命保険から減らす。
- 投資コスト(手数料)は減らすべき。対面ではなく必ずネットを使う。
- 自営業やビジネスを始めて、収入に対しての税率を下げることが最速の資産形成法
- 学び:
- NISAがない時代に書かれた本なので今では当然の長期投資や利回りの話が書かれていてそこから得れることは少なく感じる。
- 副業や独立はしない前提で書かれている?
- 住宅、生命保険と同様に車両費も減らす必要があると感じた。
- 中田敦彦が言っていた手数料ハンターの話がここでもされており、投資は手数料を安くすることが大事なことを再び理解。
2節 誰も知らない資産運用の常識
- 要約:
- マイホーム購入は一般家庭にとって不動産投資へのレバレッジと同義であり、資産運用は不動産依存となって財産三分法は不可能、長期投資が必ずしも善ではなく預金が有利な場合もあり、市場や経済は誰にも予測できず、ファンダメンタル分析やテクニカル分析も信頼できず、短期投機は投資ではなく安価なギャンブルにすぎない。
- 詳細要約:
- マイホームの購入は不動産投資にレバレッジをのと同義
- 財産三分法はマイホームを買う一般家庭には不可能。
- 不動産を買う一般家庭は資産運用はそこで終わっている(不動産に依存している)
- 必ずしも長期投資が善とは限らず、10年スケールで見ると預金が善ということもあり得る。
- 市場や、経済の動向は誰にも予測できない。
- ファンダメンタル分析は企業の粉飾や、アナリストの怠慢により信頼できないものになった。また投資としてのテクニカル分析も同じく未来を予測できるようなものではない。
- 短期投機は投資ではなく、手数料の極めて低い最高のギャンブルである。
3節 不動産の呪縛を解き放つ法則
- 要約:
- 不動産に精神的価値はない。家を買うのは不動産投資同じ。不動産投資は収益率からほかの資産運用法と同じ評価ができ、同じ基準で評価するのが基本的は資産運用法の考え方。住宅ローンで買う場合は数倍のレバレッジをかけた不動産投資のためリスクが大きいことは理解しておかなければならない。賃貸と持ち家の差は建物の老朽化のとらえ方次第でありそこに損得は発生しない。自由に対する考え方次第で選ぶ手段は変わる。
- 詳細要約:
- 家主から家を借りるのも(賃貸)、銀行からお金を借りる(マイホーム)のも経済合理的に考えれば同じ
- 同じ金融資産でも充てる場所を家賃(不動産投資)と株式配当で天秤にかけて多いほうに投資するほうが経済合理的
- 資産運用では、銀行預金、株式、債券、不動産など全ての資産を同一基準で評価することが基本となる。
- 持ち家とは自分で自分に不動産を貸しているだけで不動産投資となんら違いはない
- 帰属家賃分はマイホームのほうが有利だと言われている。
- 経済合理性という観点では地価が上がらなければローンでの購入は悪手となる可能性が高い。
- もともと住宅ローンでの持ち家購入は買い替えを前提とした資産運用法
- 学び:
- 定年を迎えて家が残っているほうが良いという人は、そこまでに賃貸と持ち家の金額差分を投資に回してたらその時の家の価値以上のお金になっているという思考が抜けている
- 不動産投資をある程度やってどういう家がコスパのいい家なのかを理解してから、最も良い物件を自分たちの家にするというのが賢い家の買い方である。
- 金融価値という視点で見たら、安い賃貸に住み、浮いたお金をより配当の高い資産運用法で増やすほうがいいと感じた。一方で50年100年と住める家であったり、価値の軸が金融以外になった場合は持ち家にもメリットがあると感じた。
4節 生命保険は損をすることに意味がある
- 要約:
- 生命保険は扶養家族の多い低所得者向けの金融商品であり、不幸な出来事が起きた時に支払われる宝くじである。その時に家族の生活を支えられない時期がある場合に加入するもの。”その期間とかかるお金” ー ”貯金” + ”公的保険支給額”=保険金として最低限の保険に加入するべき。日本の公的保険制度は手厚いため、掛け金の安い、共済やネット生保に入会する、受け取るタイミングを貯金が尽きるタイミングからにするなどして、浮いたお金を資産運用に回すほうがよっぽど合理的といえる
- 詳細要約:
- 要約 生命保険は不幸な出来事が起きた時に支払われる宝くじである。
- 所感 当然入会するものだと考えていた生命保険は毎月コツコツ宝くじを買っているのと同じだったのか…
- 要約 自分が当選したときに賞金以外で家族の生活を支えることができない時期がある場合に加入する
- 所感 今までなんとなく保険金を決めていたが何か月で建て直せて、何か月支えれればよくて、それにはいくら必要かという計算から保険金が決めれるってことですね。経済的余裕ができていたり、支える子供巣立った場合は死亡保険はいらないということになるのも改めて理解しました。
- 要約 生命保険とは扶養家族の多い低所得者向けの金融商品
- 学び 貯金があれば保険に入る必要がないということですね
- 要約 共済とネット生保を比べて安いほうに入るのが経済合理的
- 学び 今まで真剣に保険を選んだことがなかったので、調べるきっかけになりました。
- 要約 日本の公的健康保険制度は他国に比べて極めて手厚いため、必要最低限の加入が合理的。具体的には所得補償制度(休業保険)× 貯金が底をつくタイミングから支給されるものに加入しておけば最も合理的といえるだろう
- 学び 特に考えずに非合理的な保険に入っていたため、公的保険の構造を把握し、すぐに保険の入り直しをしようという考えに至りました。
- 学び:
- 毎月一定額払えばもしもの時にお金が入ってくるものでみんな加入しているから自分も入っておくという考えだったが、実際そうなったときを具体的に想像して、必要最低限入るということを学べた。
- すぐに実践できそうなこと:
- 加入保険の見直し
5節 見えない貧困化が拡がっている
- 要約:
- 子育てコストは家庭の貧困化につながっているという現実を理解するべき。生涯年収(3億円)ー税金/年金/保険(7000万円)ー住宅関連支出(7000万円)ー子供二人養育費(4000万円)-老後資金(3000万円)=9000万円。それを40年で割って年200万円。食費なども引くととても娯楽に費やせるお金はなくなる。これを隠れ貧困層という。
Part 2:人生を最適設計する「マイクロ法人」の知識
6節 国家に惜しみなく奪われるひとびと
- 要約:
- サラリーマンは国家からお金を惜しみなく奪われる人々だ。
なぜなら税金/保険制度での負担割合が年々多くなってきているからだ。
複雑な税金/保険制度の構造の歴史をよく理解するとそれが見えてくる。
もちろん今後も負担割合は増えていく可能性は高いだろう。
- サラリーマンは国家からお金を惜しみなく奪われる人々だ。
- 詳細要約:
- 要約 国民年金は得をして、厚生年金は損をする。国民年金は実質任意に比べて、厚生年金は強制+給与天引きのため、当然のように負担は厚生年金側で持つことになる。国民年金も厚生年金も個人で見れば帰ってくるが、厚生年金は半分が会社負担のため、厚生年金額の返還額で見ればマイナスとなる。年金財政は赤字である。年金制度は国民年金と厚生年金に分かれていて、厚生年金は会社と個人で半分ずつの支払いとなる。国民年金は資産運用としても悪くない制度となっているが、厚生年金はそうでもない。そのためサラリーマンは奪われる人々といわれる。
- 学び サラリーマンの実質税負担(所得/住民税、社会保険(厚生年金、健康保険))3割というのは生涯で1億円を納める重すぎる負担なことと、強制力があるため今後も自営業者と比べると税負担を増やされていくのはサラリーマンだというのを理解するべき。会社が持ってくれている負担分は本来は給与でもらうはずのお金なので得にはならない。
- 要約 労使折半により社会保険料の半額払ってくれるから得という考えだったが、本来は人件費だったという衝撃の事実を知り、”よくわからない””国の制度だから仕方ない”ではなく、すぐに税負担をどうにかしないといけないという考えになった。
- 学びまとめ:
- 新卒入社前から、給与の6割くらいが手取りが当然だという教育を受けて入社したため、多いなとは思いつつも仕方ないことだと思っていた。本章を読んで当然だからではなく、構造を理解してできることを探すということがいかに大事かが身に染みた。
- すぐに実践できそうなこと:
- 7章の方法を実践して、税負担を減らす。
- サラリーマンを捨てる。
7節 個人と法人、二つの人格を使いこなす
- 要約:
- 合法範囲で、納税額を下げ、税再分配を上げることが必要。自営業者の申告税制/多重課税式/法人の人化により歪んだ税制度の恩恵は法人に微笑む。必要経費の計算タイミングの違いによる純利益の増加、赤字法人の非課税化、配当課税の半分減税など個人でもできることを法人として実施するだけで純資産が増える。
- 詳細要約:
- 要約 公務員は再分配により幸福を実現する役割、政治家はより良い再分配の手段を謳えるものが当選する。それにはお金がいるので税徴収が増える。いわゆる恐ろしく非効率なシステム「デモグラシーのコスト」。この本質に気付いている人が多い欧州では政治関心が極低。
- 学び なんとなく意味のない政治だなと感じていたがその理由が記されていて、なるほどモヤっとしていたのはこれだったのかと頭の中がすっきりした。
- 気づき:
- 正直目からうろこな話でした。もっと早くに知っておけば生涯資産を増やせたのにと後悔しています。ただ今からでも遅くないのでマネーリテラシーを上げる努力と資産を増やす努力に力を入れていこうと思いました。
- その気づきから何を考えたか:
- 過去の医療費控除を保険証システム、マイナンバーシステムから正確に出し、メモっておく。
- 今後なにか買ったときは必ず領収書をもらい。保管場所を作り年度ごとに保管しておく。
8節 マイクロ法人で人生が変わる
- 要約:
- マイクロ法人と個人を使い分けて純資産できるだけ減らさない方法記述している。
ポイント①:所得税の発生しない範囲で給与を決定する
控除を最大化し、マイクロ法人から自分への最適年収のみを支払う。
ポイント②:所得税の発生しない範囲で家族を雇用する
専業主婦の妻を雇い年収103万以下に設定し、中小企業退職金共済で控除枠を増やす。
ポイント③:生活費を法人の経費に振替える
法人名義で生活費を支払うことで生活費の一部を経費として損金に加算し、法人税を減らす。
ポイント④:個人資産を法人名義で運用する
法人名義で資産運用することにより無課税+還付加算金を受け、資産にかかる税金を減らす。また、資産を法人に貸し付け、報酬を貸付金の返済として受け取ることで社会保険料をなくせる。
- マイクロ法人と個人を使い分けて純資産できるだけ減らさない方法記述している。
- 詳細要約:
- 要約 個人が法人を利用して合法的に税コストを下げる4つのルール「①所得税の発生しない範囲で給与を決定する」「②所得税の発生しない範囲で家族を雇用する」「③生活費を法人の経費に振替える」「④個人資産を法人名義で運用する」
- 要約 制度の歪みの代表例が法人で経費を計上しながら、自分に対する報酬にも給与所得控除(サラリーマンの経費)が認められるという経費の二重取りだ。(一つの経費が法人側の所得控除と個人側の所得控除の両方に適用されるイメージ)
- 学び
- 要約 1円で会社は作れる。300万円から事業はまっとうになる。法務局に電話すれば法人設立を手伝ってくれる。賃貸の契約もばれないのでほとんどの人は勝手に登録している。郵便局に事務所なことを言っておけば会社名が表札になくても届けてくれる。登記は大手銀行との交渉を避けるなら、信用組合/金庫に頼む。税金関係の書類提出方法は税務署に聞けばよい。法人税関係は最低年7万円のコスト。経理は自分で勉強できる。
- 要約 「1.所得税の発生しない範囲で給与を決定する」(個人)
- 自分への給与は損金になる月給とする。
- 東京都での所得税のかからない最適年収は500万円以下
- 小規模企業共済に加入して月額最大7万の掛け金を所得控除にする。
- 国民年金基金か個人型確定拠出年金(以下、ideco等と呼ぶ)に加入して月額6万8000円の掛け金を所得控除とする。
- 要約 「②.所得税の発生しない範囲で家族を雇用する」(個人、法人)
- 妻が専業主婦の場合のみ
- 103万以内に妻の年収を設定して所得税の発生しない給与枠を増やす
- 中小企業退職金共済に加入し、月3万以下の掛け金を損金とする。
- ideco等と小規模企業共済の枠を2倍にする
- 雇用の実態を税務調査で確認されることがある。
- 学び
- 要約 「③.生活費を法人の経費に振替える」(法人)
- 自宅の一部を事務所として使用し、公共料金(電気、ガス、水道料金、電話代、インターネット、書籍など)の半分を法人の経費とする
- 飲食代、車、パソコンなど仕事に必要なものだと説明できれば経費になる
- 200万円程度は適法な範囲で法人経費にできる。
- 法人名義で家を借りて、実家賃と仮家賃(社宅ガイドライン)の差額を経費とする。
- カーリースを法人名義で借り、経費とする。
- 経営セーフティー共済に加入し、月最大20万円の掛け金を損金とする。黒字時に積み増し、赤字時に解約することで法人の損益を調整もできる。
- 学び
- 要約 「④.個人資産を法人名義で運用する」(個人)
- 余ったお金を自分の法人に貸し付けて法人名義で株式運用する。無課税+還付加算金により、個人としての運用より税制メリット多。
- 学び
- 要約 最適年収の計算は「課税所得をゼロにする」「社会保険料を最小化する」により導かれる。
- 課税所得
- ”基礎控除””
配偶者控除””扶養控除””社会保険料量控除””生命保険料・損害保険料控除”+”ideco等の掛け金””小規模企業共済の掛け金”の合計を計算し、>=年収で年収を設定すれば最適年収となる。家族に支払う報酬も同様の方法で最適化できる。
- ”基礎控除””
- 社会保険料
- 国民年金と国民健康保険がある
- 国民年金は定額のため最適化できない。
- 2013年の改定で国保の保険料の最適化も困難になった。ただし方法はある。6年間という根拠がわからないが、赤字法人の場合、個人資産を法人に貸し付ける、報酬を貸付金の返済として受け取る。とすれば旧ただし書き所得がゼロになり、結果的に国保の保険料も最適化できる。
- 学び
- 課税所得
- 要約 国民年金基金と個人型確定拠出年金のどちらを選ぶかですが、現代ではリスクとリターンが少し高いのが後者で、低いのが前者というイメージのため、性格によって使い分けるのが良いでしょう。
- 気づき:
- 自分が意外にも控除を使いこなせていないと気付いた。
- 世の中の当然というものにも何とかする方法はあってそれを知らずに生きていると知らず知らずに損をしているということ
- 学生バイト時代にお客さんの社長さんがいつも領収書頂戴と言っていた理由に今気づいた。
- なぜそう思ったか:
- ほとんどの控除は自分には無関係だなという先入観からほぼ控除の申請をしておらずみすみすおかねを減らしていたことに気付いた。
- 当然なんともできないと思っていた税金にも何とかする方法があって、知らずに生きてきたために手元に残るはずだったお金が手元に残っていないから
- 生活費を経費に回して、税を減らし結果的に純資産を増やすという考え方が自分にはなく、純資産を増やす努力をしていなかったなと思ったから。
- その気づきから何を考えたか:
- 日本では当然とされている考え方や制度にも疑問を持ち、常に自分のプラスに働くほうに変えれる方法はないかというマインドを持つということを学んだ。
- 実務や生活にどう活かすか:
- 日本の税制度や控除を理解し、法人を設立し、それらを利用し、純資産を増やす努力をする。
9節 不可能を可能にする奇跡のファイナンス
- 要約:
- 事業のキャッシュフローを考えるうえでファイナンス(資金調達)が必要となるが、個人では不可能な低金利公的機関(自治体など)からの融資も法人成りすると可能となる。もちろん条件はあるが、公的機関から融資を受ける際の各機関の構造に着目すれば、信用保証協会の条件を満たすのが最も確実なため。融資申し込み時は信用保証協会を訪れ条件を満たしているか確認するのが効率的となる。書類さえ用意できればという機関のため、一見書類の用意が難しそうでも、工夫すればやりようはいくらでもある。また毎月決められた期日までに返すことでより多くのお金を融資してもらえるようになる。これにより民間の融資年利では考えられないような低金利でファイナンスすることができるようになる。
- 詳細要約:
- 要約 国の助成金や補助金を違法に利用すると儲けることができる。
- 学び
- 要約 貸し出し金利は調達金利とリスクで決まる。
- 学び
- 要約 マイクロ法人になる場合まずは事業のキャッシュフローを考える。必要な資金には運転資金と設備資金がある。ファイナンス(資金調達)にはエクイティファイナンス(株式発行)とデッドファイナンス(銀行借り入れや社債発行)がある。自営での失敗で多い原因は事業の基本設計とファイナンスに関するもの。知識なくファイナンスを行うと高金利で借りることになりいずれ行き詰る。
- 学び 金融機関には民間金融機関と公的金融機関がある。民間に比べると公的機関は低金利でのファイナンスが可能であり、個人で受けれる公的機関の融資には住宅ローンくらいのものだが、法人になったとたん様々な公的機関から融資を受けられる。ここに黄金の羽がある。
- 気づき:
- 情報収集と構造を理解することの大切さに
- なぜそう思ったか:
- 法人成りしたら公的機関からお金を借りれるとう情報がなければ。また、公的機関融資の仕組み、ステークホルダーを把握し、何をもって融資条件が達成されるのかという構造を理解しなければ、低金利でファイナンスする(黄金の羽を拾う)ことはできないから。
- その気づきから何を考えたか:
- 情報収集、事実確認、推論という基本的な論理的思考が改めて大事なことに気づいた。借金をして、それを運用し増やすという資産を増やす方法の基本に借金は必ず必要なのでここで知れてよかったと感じた。
- 実務や生活にどう活かすか:
- 事業ファイナンスをするときは公的機関を使用できるかの情報収集をし、より低金利な融資の条件を工夫してクリアする。
10節 税金について知りたいほんとうのこと
- 要約:
- 税コストを下げる方法に節税、グレーゾーン、脱税があり、それらの違いは説明責任の違いだ。本章では説明責任のあるグレーゾーンの方法(裏金の作り方)を教授している。前提として決算が確定した所得に対して発生する税を払わないのは脱税となるが、本書で紹介する方法は、決算が確定する前に決算調整して裏金(税金のかからないお金)を生むというという日本の制度の歪みからくる、節税(グレーゾーン)である。裏金とは実際の所得と、過小に申告された税務上の所得の差額。裏金の作り方は2種類だ。売り上げの過小申告か経費の水増し。一般法人は後者が現実的。マイクロ法人の場合決算を赤字にするほうがメリットが多い。無税で資産運用で来たり、法人税を払わなくて済んだり、面倒な税務調査を受けなくて済むからだ。経費の水増しで最もよく使われるのは取引先に早めに請求書を起こしてもらうこと。支払いは後でも税法上は問題になりません。また、売り上げ付きを決算後にずらすのも同様によく使われる。
- 詳細要約:
- 税コストを下げる。節税と脱税の違いは説明責任の違い。裏金は売り上げを過少申告、経費のかさましにより作られる。
- 裏金の作り方の良手と悪手の説明、注意点
- 零細法人、マイクロ法人の場合決算の目的は赤字にすること。赤字にすると税務調査が入らない。つまり裏金を作りやすい。ついては裏金を記録の残らない生活費にあて、給与(表金)を法人に貸付て運用するとマネーロンダリングの完成
- 決算調整で赤字にする方法のbasicは取引先に早めに領収書を起こしてもらうこと。そういった取引先をいくつか持っておくと良い。同様に赤字を黒字にも調整する粉飾決算もできるがこちらは負のスパイラルに陥るので悪手。
- 気づき:
- 裏金というものが合法的に作れて、それがいかに大切かをに気づけた
- なぜそう思ったか:
- 本書を読んでいる目的に純資産を増やし方を知るという点があるが、本章が最も効率的かつ、インパクトの大きな純資産の増やし方だと思ったため。
- その気づきから何を考えたか:
- 法治国家、資本主義のこの国では、黄金の羽を拾うということは法をかいくぐって、資本を増やすという本書で最も言いたい本質的なことが書かれている。
- 実務や生活にどう活かすか:
- 合法の範囲をきちんと理解し、その範囲内で最大限の節税(裏金)を作っていく。
- また法人だけではなく個人でもそういった考えが適用できないかを考える。
11節 税務調査の裏と表
- 要約:
- 本章では税務調査の構造と逃れ方(黄金の羽の拾い方)を教授している。税務調査には強制と任意があり、前者は高収入企業向けのみ、マイクロ法人は後者になる。典型的な6つの項目を約1日かけて調査される。税務署は税金の取れそうな黒字企業から調査対象を選びます。また、税務署OBの税理士と税務署は癒着しているため、彼らを顧問にすると無理な徴税は避けられる。国税庁とも癒着しているため(天下りなど)国税庁、税務署、税理士の構造は得をする人と損をする人の溝を広げているのです。
- 学べたこと:
- 公的機関は手ぶらで信じれるものではなく、構造を把握し利用するものだと気づいた
- 合法に裏金を作るだけではだめで、税務調査をされないという工夫も必要だと気づいた
- その学びから何を考えたか:
- 税務行政が歪んでいるため公平に税務調査がされていなく、損をする人、得をする人の差が生まれていることが本章で学べた。ほかの行政も同じだとすると、公的機関の配当には平等性などなく、いかに黄金の羽を拾うかということのほうが大事だと考えた。
- 実務や生活にどう活かすか:
- 裏金を作った際には上記の方法で税務調査を逃れる。
Part 3:人生を最適設計する「働き方」
12節 クリエイティクラスとマックジョブ
- 要約:
- 企業特殊技能しか身に着けられず、一般的技能の欠如しているサラリーマンが労働市場に放り出される残酷な世界で生き延びるには、好きを実現するニッチを見つけ、スペシャル(専門)に特化し、会社に依存せずに市場から長く富を得ることが知識社会での働き方であり、経済的独立を実現する方法だということを教授している。
- 学べたこと:
- 終身雇用の時代は終わり、個人価値が重視される時代が来ていること
- 好きを仕事にするという考え方
- その学びから何を考えたか:
- 好きなことかつ、長く働ける仕事を選べば、成功しなくても、大失敗しなければお金に困ることはないし、もし成功したらもちろんお金に困ることがないという、精神的にも経済的にも優しい考え方だと考えた。
- 実務や生活にどう活かすか:
- 副業や、企業の事業を考える際は、本章の考え方を思い出し、稼げそうだけではなく、できるだけ好きな続けられそうなものを選ぶことにする。
- 疑問点 「なぜ?」「本当に?」「他には?」:
- 企業で働いていると最低限企業特殊技能は身につけないといけないため、身に着けたうえで意識的に一般的技能を身につけに行くのが良いと感じた。
- 稼ぐこと好きな人は好きを仕事にするではなく、稼げる仕事を好きになるという目的と手段が逆転させることもできるため、自分が何が好きかをまずは棚卸するのが大事だと感じた。
全体
- 全体まとめ:
- 本を読むことの大切さが身に染みてわかった。編集者はここ最近ビジネス書を読み始めたばかりでありなんとなく読んでいることが多い。本書は初版2002年、改訂版2015年という10年以上前に出版された本にもかかわらず現代でも通用するどころか、未来にも通用する内容がほとんどとなっている。現代ではNISAなどが開始され要約、資産運用が注目されるようになった。もし本書を出版当時に読みインデックスファンドでの資産運用、個人と法人の使い分けをすぐに始めていれば億万長者になること夢ではなかっただろう。実際は当時この本を読んでも、得体のしれない手法ばかりが書いてあり、食わず嫌いしていたかもしれないが、今本書で記載されていることが現実になっている答え合わせができていることがこういった気づきにつながっているのだとも思う。
- 新しい本を読むということも大切だと感じた。本書は名本だが出版10年後に読んでもすでに世に知れ渡っている事実も多いため、当時に比べて価値は薄れている。最も価値の高い出版後すぐに読むべきだと感じた。
- 本の選び方も重要だと感じた。本の出版数が増えかつ、本を読む時間も限られている現代では、すべての本を読むのは現実的ではないため、本書のような名本を見極める情報収集力と目利き力を鍛える
実践したいこと
すぐに実践したいこと
- 生命保険を見直す
- 安易にマイホームを購入しない。
時間をかけて実践したいこと
- 好きを実現するニッチを見つけ、スペシャル(専門)に特化する。
- マイクロ法人を作る